この記事では、Gensparkの情報漏洩の詳細、そして原因と対策について解説します。
2025年に入り、AI検索エンジンとして注目を集めているGensparkですが、同時に深刻なセキュリティ問題が相次いで報告され、情報セキュリティ業界で大きな話題となっています。
生成AIの学習を希望される方は以下の公式サイトを、Gensparkの情報漏洩の原因と対策について知りたい方はこの記事を確認していただき、同じ悩みを抱えている方の参考になれば幸いです。
オンラインAIプログラミングスクール Aidemy Premium
2025年に発覚したGensparkの重大なセキュリティ問題
LayerX社による脆弱性報告(2025年9月)
2025年9月、サイバーセキュリティ企業LayerXによる詳細な調査で、Gensparkが他の主要ブラウザと比較して極めて脆弱であることが判明しました。
Skywork.aiの報告によると、
- 脆弱性成功率90%超:悪意のあるウェブページの90%以上でセキュリティが突破される
- Chrome比較で圧倒的劣位:Google Chromeなど従来ブラウザと比べて著しく高いリスク
- フィッシング攻撃への脆弱性:特にフィッシング攻撃に対する防御が不十分
エンドユーザーが通常の検索や閲覧を行うだけで、不正サイトに誘導されて情報を抜き取られる危険性があり、個人・企業を問わず看過できるものではありません。
IT担当者や経営層からは「想定外のリスク」「導入再検討すべき」といった声が上がり始めています。
Androidアプリの深刻な権限問題(2025年8月)
2025年8月の調査では、Genspark Androidアプリケーションにおいて権限管理の重大な欠陥が発見されました。
- 過度な権限要求:アプリの機能に対して不必要に多くの権限を要求
- データアクセスの透明性不足:どの情報にアクセスしているかが不明確
- ユーザーフロー設計の問題:セキュリティを軽視した設計
本来アプリの機能とは関係の薄いマイク、連絡先、位置情報など、過剰ともいえる権限を要求していたことが報告されています。
企業の業務端末やBYOD環境で利用された場合、組織全体の情報資産が巻き込まれるリスクがあるため、専門家からは「インストール自体を控えるべき」との警鐘が鳴らされています。
プライバシーポリシーの分散問題
Gensparkのプライバシー保護には構造的な問題があります。
- 複数ドメインへの分散:
genspark.imと親会社MainFunc Inc.で政策が分離 - 統一性の欠如:AI製品自体に対する明確な統一ポリシーの不在
- 透明性の不足:データの取り扱いに関する詳細情報が不十分
ユーザーにとっては「同意したつもりのない範囲まで情報が利用されるのではないか」という不安が残り、企業コンプライアンスの観点からも問題視されています。
データを預けるサービスとしての透明性や一貫性が欠けている点は、信頼回復の大きな障壁となるでしょう。
情報漏洩のメカニズムと具体的リスク
AI学習データへの機密情報混入
Gensparkを業務利用する場合、入力した情報がAIの学習データに組み込まれる恐れがある点は非常に重大な懸念材料です。
リスクシナリオ:
企業の財務データ → Genspark入力 → AI学習データ化 → 他ユーザーへの情報漏洩
例えば、社員が財務データや顧客情報を検索や要約のために入力した場合、それが内部処理を経てデータベースに保存され、将来的に他ユーザーとの対話や生成コンテンツを通じて漏洩するリスクがあります。
AIの特性上、一度取り込まれた情報は完全に消去することが難しく、情報管理担当者でも追跡が困難です。
特に法務・医療・金融といった守秘性の高い業界では、外部サービスへの入力自体が社内規定違反に該当することも少なくありません。
「便利だから」と安易に使い続けると、知らない間に内部情報が第三者に露出する可能性があり、企業価値や信用を失う深刻な結果を招く恐れがあります。
「Call For Me」機能のプライバシー侵害
GensparkのSuper Agent機能の一つである「Call For Me」は、ユーザーの代わりに予約や問い合わせを行う便利なサービスとして紹介されていますが、その裏には看過できないプライバシーリスクが潜んでいます。
- 音声データの収集:通話内容の録音・保存の可能性
- 個人情報の自動取得:予約や問い合わせ時の個人データ流出
- 第三者への情報提供:通話相手への意図しない情報開示
予約代行や問い合わせといった行為は利便性の高い一方で、情報のやり取りが自動化されることにより、利用者がどの範囲まで情報を渡しているのか把握しづらくなります。
安心して使えるサービスと捉えるには、現状では説明も対策も不足しています。
ブラウザレベルでのデータ収集
GensparkはAI統合型ブラウザとしての機能を備えていますが、その利便性の裏で、ユーザーの行動を従来のブラウザより詳細に記録している可能性があります。
- 閲覧履歴の詳細分析
- 入力テキストの全記録
- 画面操作パターンの追跡
こうした情報が外部サーバーに送信されている場合、利用者側で確認・制御することは極めて困難です。
ビジネス利用においては、競合他社への情報流出や内部不正のきっかけになり得るため、セキュリティポリシーの観点から導入を見直す企業が増えています。
日本企業への影響と法的リスク
個人情報保護法違反のリスク
日本国内でGensparkを利用する場合、個人情報保護法に抵触する可能性が指摘されています。
- 第三者提供の同意不備:ユーザーデータの海外サーバー送信
- 安全管理措置の不備:適切なセキュリティ対策の欠如
- 利用目的の明示不足:収集データの使用目的が不明確
企業が業務で導入した場合、本人同意なしの第三者提供に該当し、行政処分や損害賠償のリスクを抱える可能性があります。
法令遵守を重視する企業ほど、利用継続はリスクと判断せざるを得ない状況です。
2025年の法改正への非準拠
2025年に施行された改正個人情報保護法では、AIサービスを提供する事業者に対し、従来よりも厳格なデータ管理と透明性が求められるようになりました。
しかしGensparkの現在の仕様は、こうした要件を十分に満たしていないと懸念されています。
特に、取得したデータの保管場所や利用目的の明示、第三者提供に関する説明責任といった基本的なポイントにおいて不備が目立ちます。
さらに、AIによる自動処理が行われる場合には、利用者に対する説明義務や拒否権の提示が必要ですが、それらが明文化されている形跡も乏しいです。
企業がこの状況を見落として導入すれば、知らないうちに法令違反状態に陥る可能性もあり、監査や訴訟リスクを抱える恐れがあります。
コンプライアンスを重視する場合、現状のままでは採用判断が難しいといえるでしょう。
企業が今すぐ実施すべき対策
即座に実行すべき緊急対策
Gensparkに関するリスクが明らかになった今、企業や組織は被害を未然に防ぐための緊急措置を早急に講じる必要があります。
多要素認証の全面導入
対象:すべての重要業務アカウント
方法:SMS認証、認証アプリ、生体認証の組み合わせ
期限:即座に実施
Gensparkの業務利用禁止
対象:全従業員
内容:機密情報を含む業務でのGenspark使用の全面禁止
周知方法:緊急通達、セキュリティ研修
これらの対応は「大げさ」ではなく、現実的な被害を防ぐための初動として必要不可欠です。
中長期的なセキュリティ強化策
応急的な対処だけでは、AI関連サービスによる情報漏洩リスクを根本的に解決することはできません。
そこで中長期的な視点で、組織全体のセキュリティ体制を再構築する取り組みが重要になります。
2024年の調査では、66%の組織が今後1年間で内部からのデータ漏洩リスクの増大を予測しています。
これに対応するため、「誰も信用しない」を基本とするゼロトラストモデルの導入が急務です。
AIガバナンス体制の構築
生成AIの企業利用に関する包括的なガイドライン策定が必要です:
- 利用可能なAIサービスのホワイトリスト化
- データ分類に基づく利用制限
- 定期的なセキュリティ監査の実施
従業員教育の強化
シャドーAI(非公式AI利用)のリスクを周知し、適切なAI利用方法を教育する包括的な研修プログラムの実施が重要です。
これらの取り組みを継続することで、AI時代に適応した堅牢な情報管理体制を構築できます。
代替ソリューションの検討
Gensparkの利用停止や制限を実施する場合、単に排除するだけではなく、安全性が確認されている代替サービスへの移行を検討することが現実的な対策になります。
セキュアなAI検索ツール
Gensparkの代替として、以下の要件を満たすツールの採用を検討してください:
- データローカライゼーション:日本国内でのデータ処理
- エンタープライズ契約:法人向けプライバシー保護
- 透明性のあるプライバシーポリシー
- 第三者セキュリティ認証(ISO27001等)
選定プロセスでは、機能性よりもまずセキュリティ基準と運用体制を優先し、自社の業務環境に適した選択を行うことが不可欠です。
個人ユーザー向けの安全対策
既存アカウントの確認
すでにGensparkを利用している個人や企業にとっては、まず現状のアカウント管理を見直すことが重要です。
1.即座にアカウント削除申請を実施
2.使用していたパスワードを他サービスで使いまわしていないか確認
3.入力した個人情報の記録を作成し、監視体制を構築
この作業は面倒に思えるかもしれませんが、被害の有無を判断するための初期ステップとして極めて重要です。
放置してしまうと、後から問題が発覚した際に対応が遅れ、大きな損失につながる恐れがあります。
情報漏洩の監視
Gensparkを過去に利用していた、あるいは現在もアカウントを保持している場合、情報漏洩の有無を定期的に確認する体制づくりが欠かせません。
特に、クレジットカード情報や本人確認書類、連絡先などを入力した記憶がある方は、万一のリスクに備えてクレジットモニタリングやダークウェブ監視サービスの利用を検討するべきです。
たとえば、クレジットカード会社の不正利用通知サービスや、漏洩情報を検知する外部サービスを併用することで、被害を早期に発見できます。
また、パスワードやメールアドレスが第三者に悪用されていないか定期的にチェックする習慣も重要です。
「自分は大丈夫」と思って放置してしまうと、異変に気づいた頃にはすでに被害が拡大しているケースも珍しくありません。事前の備えが最大の防御策になります。
セキュアな代替手段
GensparkのようなAI検索・チャットサービスを使いたい場合でも、安全性が確認された代替ツールを選ぶことで、情報リスクを抑えながら利便性を確保できます。
- Perplexity:透明性の高い引用システム
- Microsoft Copilot:エンタープライズ級のセキュリティ
- Google Bard:Googleの堅牢なセキュリティインフラ
重要なのは、どのサービスが自分の情報をどのように取り扱い、どこに保存するのかを事前に理解した上で選ぶことです。
なんとなく便利そうだから、と使い始めるのではなく、信頼性を軸に判断する姿勢が求められます。
2025年のサイバーセキュリティトレンド
統計データが示す深刻な現状
2025年上半期だけでも、日本国内で公表されたセキュリティインシデントは247件に達しており、1日あたり約1.4件のペースで何らかの情報漏洩や不正アクセスが発生しています。
特に大企業では、一度被害が起これば平均で7億円を超える損失が発生するとされており、信頼の失墜や株価の下落、顧客離れなど二次的な影響も無視できません。
さらに問題なのは、表に出ていない「潜在的な被害」が存在する点です。
企業の規模にかかわらず、従業員のミスや外部サービスの脆弱性が原因で、知らないうちにデータが流出しているケースも増えています。
こうした背景を踏まえると、AI関連サービスの安全性を見直すことは、今や特定企業に限った課題ではなく、日本全体で考えるべき社会的テーマだといえるでしょう。
AI関連インシデントの急増
特に注目すべきはAI絡みの情報漏洩件数が1年で2倍以上に増加していることです:
- チャットボットへのデータ入力:前年比156%増
- シャドーAI利用:管理の目が届かない状況で急拡大
- プロンプトインジェクション攻撃:新たなサイバーセキュリティ脅威として浮上
管理者が関与していない環境でデータが扱われるため、漏洩に気づかないまま事態が悪化することもあります。
新たな脅威としてプロンプトインジェクション攻撃が注目されています。これは入力内容を悪用して不正操作を誘発させる手口で、従来のセキュリティ対策では防ぎにくい点が問題です。
「便利だから」「誰も使っているから」と油断してしまうと、取り返しのつかない事態につながる恐れがあるため、企業も個人も慎重な姿勢が求められます。
Gensparkの情報漏洩の原因と対策まとめ
Gensparkに関する一連の問題は、単に一つのアプリケーションや企業体質の欠陥という枠を超え、AI活用時代における情報セキュリティの盲点を浮き彫りにしています。
重要なポイント
- 即座の利用停止:業務でのGenspark使用を直ちに停止
- 代替ソリューションの導入:セキュリティが確認されたツールへの移行
- 包括的なAIガバナンス:全社的なAI利用ガイドラインの策定
- 継続的な監視体制:情報漏洩の早期発見システムの構築
今求められているのは、「危なそうだから使わない」という短絡的な判断ではなく、サービスの構造やデータの流れを理解した上で、どこにリスクが潜んでいるのかを冷静に見極める姿勢です。
すぐに業務利用を停止すること、代替手段の導入を検討すること、社内にAIガバナンスを構築すること、そして漏洩監視や教育体制を整えることが、総合的な解決策となります。
情報セキュリティはコストではなく、企業と個人を守るための必須インフラです。
今この問題に正面から向き合うことで、将来的な被害や評判の失墜を未然に防ぎ、安心してAIを活用できる土台を築くことができます。
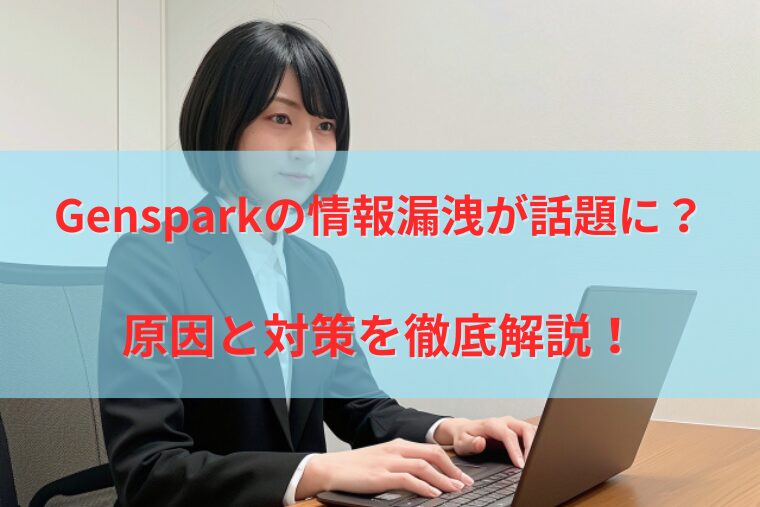

コメント